
▼ノートス教育コラム6月号
【充実した夏休みを過ごすには~小学生編~】


▼目次 好きなところから読めます
子どもが計画を立てない理由①
立てるという発想がない・立て方が分からない
計画は、大人にとっては当たり前ですが、時間軸の焦点が「今現在」にある子どもにとっては未知の世界。
いきなり計画を立てられる子も中にはいますが、ほとんどの場合、
「計画とは何か?」をまずは教えることが必要です。

身近な例で見てみましょう。
![]() 目標(ゴール)に到達するためにどのくらいやらなければいけないのかを考えるのがポイント
目標(ゴール)に到達するためにどのくらいやらなければいけないのかを考えるのがポイント![]()
「今の自分ならこれくらいできそう」というのを優先して考えてしまうと目標に到達できない可能性が高くなる。
例
△ワーク1日1ページずつならできそうだから、そうしよう。
◎100点をとるために、テスト範囲のワークを3周練習しよう。そのためには、1日3ページずつ進めないとな。
子どもが計画を立てない理由②
計画通りにこなす自信がない
「計画を立ててしまったらその通りやらないとダメだ。それだったら最初から立てない方が良いのではないか。」
という考え方になってしまっている子どもをたくさん見かけます。
根本には、
・「自分で決めたことなのに、何でちゃんとやらないの?」と怒られた
・前に計画を立てた時にその通りできなかったから自信を無くしている
といった経験があるようです。

しかし、計画は一度決めたら変更不可ということではありません。理由①の表5にもあるように、実際にやってみて、「うまくいっているかの確認と修正」は必要です。
修正してもOKと柔軟に考えることで、計画に対する心のハードルはだいぶ下がるかもしれません。
子どもが計画を立てない理由③
立てるメリットが分からない
「計画=行動制限」やりたいことが出来なくなるんじゃないか?というマイナスイメージを持っている子もいます。

本当は逆で、
計画を立ててあるからこそ、「今日はここまで勉強をしたから、あとは自由時間」と気兼ねなく満喫できるという大きなメリットがあるのですが…
しかし、これも目標達成のための計画であることが前提。
子ども本人が「テストでいい点数をとりたい」「検定に合格したい」などと思っていない、つまり達成したい目標がない場合には、計画実行のせいで自由時間が減るだけなので、メリットを感じにくいのです。
「子どもが計画を立てない」はこれで解決
初めは大人のサポートが必須
①計画って何?を教える!
計画の手順表を参考に、大人が教えながら一緒にやってみましょう。
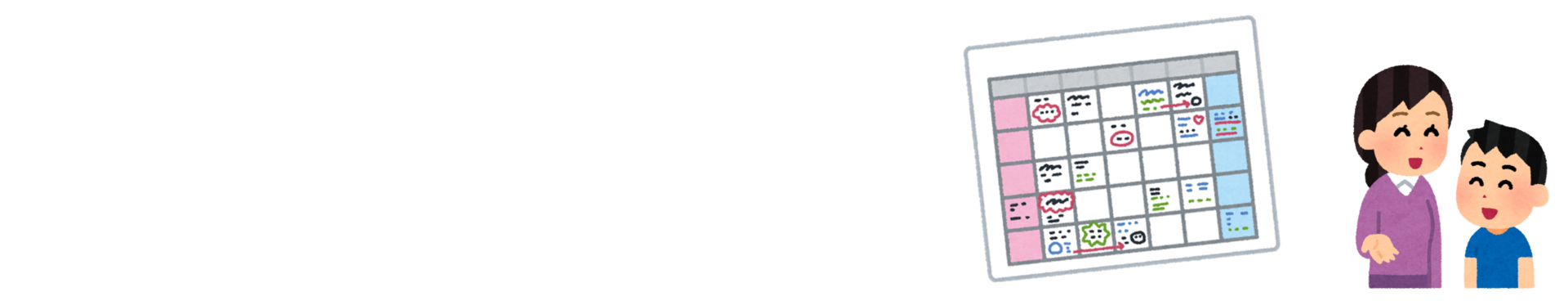
②目標を明確にする!
「理科を得意にする」など曖昧なものではなく、〇点以上など明確にした方が良いでしょう。
また、高い目標を持つのは悪いことではありませんが、その時の子どもの現状を踏まえて、達成しやすいものを設定しましょう。
例
「社会の小テストで再テストにならない」「算数のカラーテストで80点以上とる」など。

③短いスパンの計画(土日の学習計画など)から実行する練習を始める
今日は計画通りできた!という積み重ねが自信になります。また出来なかった場合は原因を一緒に考え、必要であれば修正をしましょう。
➨「計画した方がうまくいく」という成功体験につながる!

![]() せっかく立てた目標や計画がうやむやにならないように。いつでも見返せるように紙などに書いて貼ると良いでしょう
せっかく立てた目標や計画がうやむやにならないように。いつでも見返せるように紙などに書いて貼ると良いでしょう![]()



立てた計画がうまくいかない理由①
誘惑に負ける
毎日遊んでばかりいた結果…
🌻夏休みの宿題が最終日まで残っている
🌻ドリルやワークの提出期限が間に合わない
🌻翌日の持ち物の確認をしないで当日朝バタバタする
など、この子大丈夫?と心配になってしまうことがあるかもしれません。
しかし、「先を考えて行動する力」は大人になるにつれて徐々に発達してくるもの。特に小学生のうちは、「今が楽しい」を優先してしまうことが多いです。

また、子どもは時間の感覚がまだ育っていないため、
・朝に持ち物の準備をして間に合うかどうか
・今日は8/21で夏休みのワークが1ページも終わってないけど間に合うかどうか
ということが、そもそも想像しにくいのです。
「立てた計画がうまくいかない」はこれで解決
誘惑を遠ざける工夫
・家庭内でのルールを作る
楽しいこと(ゲームやスマホ)は、やるべきこと(勉強や習い事の練習など)をやってからなど
・誘惑のない環境を作る
スマホを保護者に預ける、塾に自習に行くなど
▼ノートス教育コラム5月号
【スマホ中心の生活だったAくんの成績が上がった話~ノートスの学習相談で変わった体験談~】

立てた計画がうまくいかない理由②
そもそも無理な計画を立てている
テストまでにワークを3回繰り返し解きたい。
今日はテスト10日前だから・・・1日30ページやればいいんだな!
ところが実際取り組んでみて無謀だったことに気づきます。

うまくいかないことが多いほど自信が減っていき、「こんなことなら計画なんて立てない方が良かった。」と逆効果に感じてしまうことも。
「立てた計画がうまくいかない」はこれで解決
計画の再調整
計画を立てない理由②にもつながりますが、そもそも計画というのは、実行してみて反省・振り返りをして再調整するもの。
一度決めたものを貫き通さなければいけない、貫けなければもうダメ!とすぐにあきらめるのではなく、次に生かすことが大切です。


計画力もスモールステップで
小学生からできる「計画力」育成のススメ
ステップ①
ドリルやワークの提出期限を意識した計画を立ててみよう!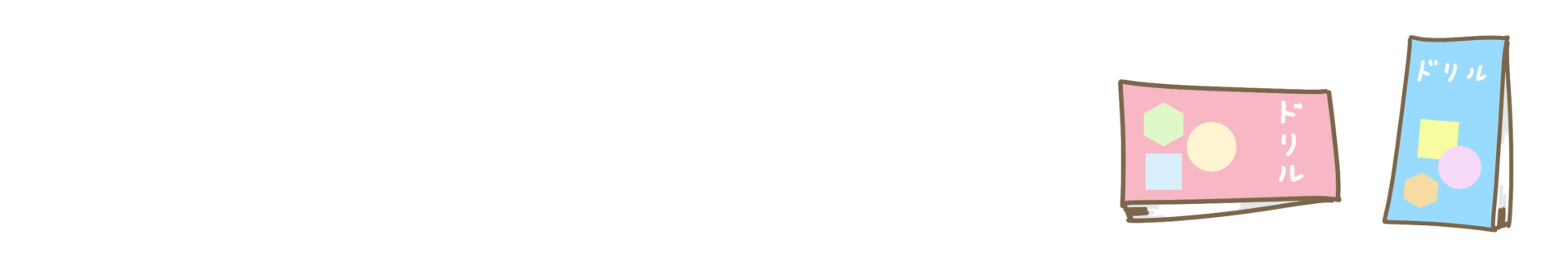
中学生では、定期テスト当日などにワークの提出期限が設けられていますね。
小学生では、だいたい4年生くらいから、学校の先生が、ドリルの提出期限を決めて、子どもたちに告知するようになります。
そこで、
・何日間で
・どのくらいの量を
取り組まなければならないのかを、まず子どもに気づかせることから始めます。
 へえー、7月18日までに、計算ドリル15番までを提出しないといけないんだね。
へえー、7月18日までに、計算ドリル15番までを提出しないといけないんだね。
 うん。まだオレ5番までしか終わってないんだ。えへへ。今日は6番をやろうっと。
うん。まだオレ5番までしか終わってないんだ。えへへ。今日は6番をやろうっと。
 そっかあ。ところで、今日は7月14日だね。あと何日で提出なの?
そっかあ。ところで、今日は7月14日だね。あと何日で提出なの?
 えーっと、あと4日かな。
えーっと、あと4日かな。
 あと4日だと、間に合うかなあ?
あと4日だと、間に合うかなあ?
 あと4日で、オレ5番までしか終わってないから…あれ?あと10ページもある!!
あと4日で、オレ5番までしか終わってないから…あれ?あと10ページもある!!
 そうだね。一度にやると大変そうだね、毎日何ページずつやったらいい?
そうだね。一度にやると大変そうだね、毎日何ページずつやったらいい?
 えーっと、10÷4=2.5だから、3ページやれば、大丈夫?
えーっと、10÷4=2.5だから、3ページやれば、大丈夫?
 そうだね。がんばって!応援しているよ!
そうだね。がんばって!応援しているよ!
コツは、先生や保護者が一方的に全部計画を立てないことです。
誰かに決められたものには反発したくなってしまいます。
「子ども自身が気づき、決めた計画を、実行するのを見守る」という形が一番良いですね。
※忘れやすいタイプのお子さんなら、今日の計画はどうだったっけ?などと思い出させる声かけはしても良いかもしれません。
ステップ②
テストの目標点達成を意識した計画を立ててみよう!
中学生なら定期テストや教科ごとの小テスト
小学生なら全校漢字テストや計算テストなど
 〇月〇日に50問テストがあるんだね!
〇月〇日に50問テストがあるんだね!
 うん。80点以下は再テストなんだって。それはいやだなあ。
うん。80点以下は再テストなんだって。それはいやだなあ。
 そっか。80点以上はとりたいんだね。じゃあ準備をした方がいいね。
そっか。80点以上はとりたいんだね。じゃあ準備をした方がいいね。
 うん。漢字ドリル〇番~〇番から出るんだって。
うん。漢字ドリル〇番~〇番から出るんだって。
 おお、そうなんだ。じゃあ、この前みたいに、毎日何ページやるか、考えておいた方が安心だね。
おお、そうなんだ。じゃあ、この前みたいに、毎日何ページやるか、考えておいた方が安心だね。
 もう考えてるよ♪毎日1ページやれば間に合いそうだよ。
もう考えてるよ♪毎日1ページやれば間に合いそうだよ。
 さすがだね!ところで、一回やっただけで覚えられそう?
さすがだね!ところで、一回やっただけで覚えられそう?
 うーん、最初にやった漢字は忘れちゃうかもな。再テストは絶対イヤだな。
うーん、最初にやった漢字は忘れちゃうかもな。再テストは絶対イヤだな。
 じゃあ、ドリルを2回繰り返しやってみるのはどう?
じゃあ、ドリルを2回繰り返しやってみるのはどう?
 えー、そんなにたくさんできるかな。自信ないな。
えー、そんなにたくさんできるかな。自信ないな。
 間違えたところだけ、2回繰り返すっていうやり方もあるよ。
間違えたところだけ、2回繰り返すっていうやり方もあるよ。
 それならできるかも。やってみる!
それならできるかも。やってみる!
🌻ステップ①と②の違い🌻
ステップ①:目的がドリルやワークを終わらせて提出すること
ステップ②:終わらせることだけでなく、80点という目標のために何をすべきかも考える必要がある
小学生、中学生、高校生と年齢が上がるにつれてタスクはハードになっていきます。 そして計画に追われるようになると「目の前の課題を終わらせる」ことにだけ焦点を合わせがちになります。
そして計画に追われるようになると「目の前の課題を終わらせる」ことにだけ焦点を合わせがちになります。
「終わらせる」だけが習慣化してしまうと、頑張っているのになぜか成績が上がらないという状態に陥る場合があります。
▼ノートス教育コラム2月号
【勉強の成果が格段に上がるコツ~意識改革編~】

くり返しになりますが、そもそもが「何のための課題なのか?」という当初の目標を忘れないことが大切です。

はじめから計画通り実行できる子ばかりではありません。
1日に学習できる量もお子さんによってちがいますので、「ここまでできたらほめる」のハードルは、なるべく低く設定しておいた方が良いでしょう。
▼ノートス教育コラム10月号
【子どもの自信が育つ「ほめ方」のコツ!】

中学生になったら?
小学生で身に付けた「計画力」+αで目標達成にさらに近づこう
中学生になって初めての定期テストでは学校で計画表が配られます。
「もうすぐ定期テストです。しっかりと計画を立てて家庭学習をしましょう。」
そこで、今まで計画を立てる経験がなかった子どもが、初めて計画を立ててみると…
・好きな科目ばかり勉強しようとする
・ワークをやることは決めているが何ページやるかは決めていない(できる分だけやる)
・ワーク1日30ページなどの無謀な計画を立てている
そしてさらには計画倒れ…
原因は、見積の甘さ・やる気のムラ・優先順位が不明確などなど
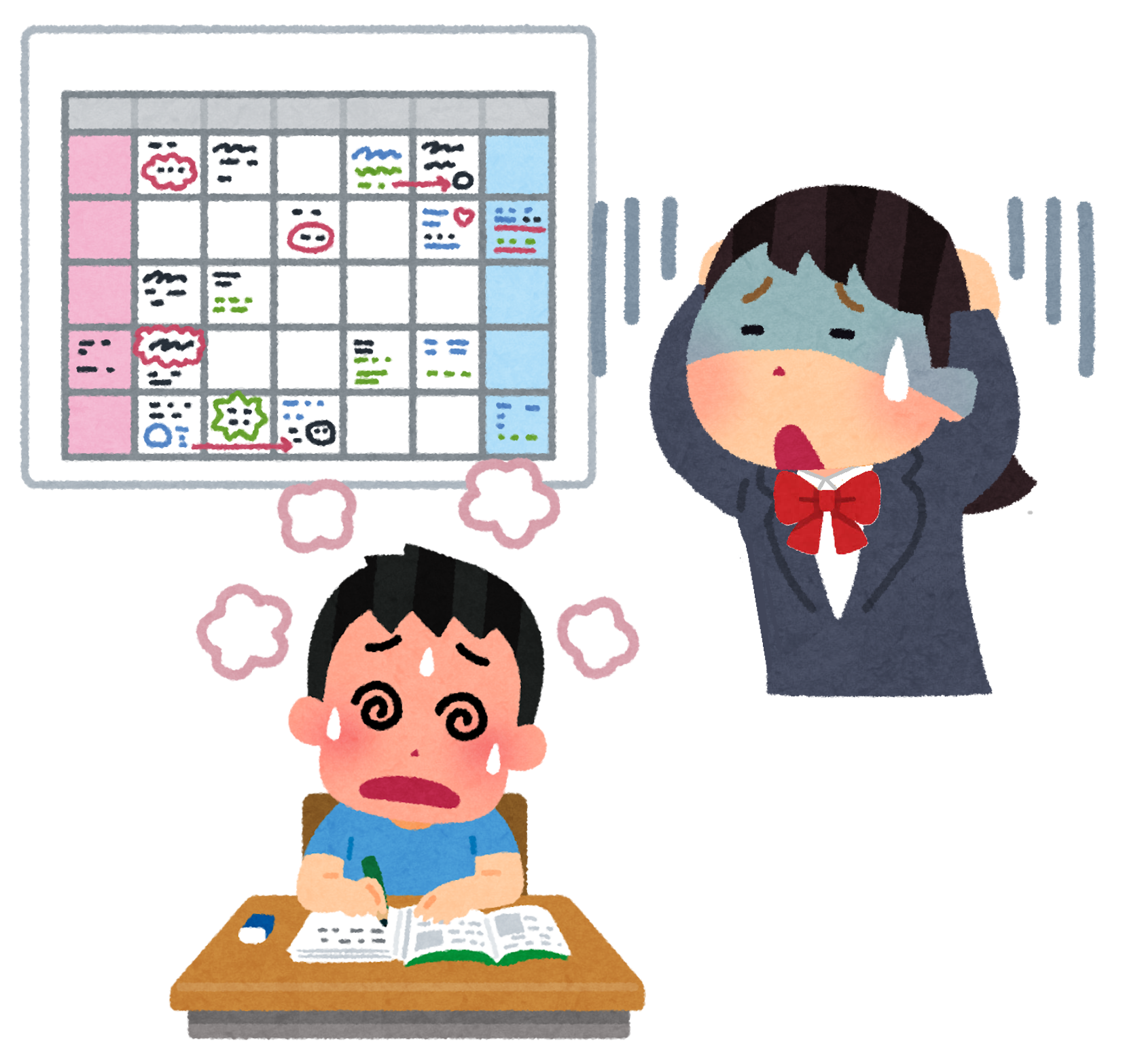 計画を立て➨実行する
計画を立て➨実行する
ということの難しさをここで痛感する子が多いのではないでしょうか。
大きな原因の1つは小学校のテストとの違い
そんな中1の壁を乗り越えるためにも、小学生のうちから少しずつ計画することに慣れておきましょう。
①教科数が多い
小学生の時は、同時に何教科もテストをするということがありません。しかし、中学校では英語・数学・国語・理科・社会の5教科のテストが2日間に分けて行われることが多いです。
②テストに向けて勉強する内容が多い
英語ひとつとっても
・英単語を覚える
・ワークの問題を解く
・先生がテストに出るって言っていたプリントを解く…
のように、やらなければいけないことが複数あります。
そのため、あれもやろう、これもやろうと思っていても、計画として書いておかないとやり忘れてしまいます。
ワークを3回繰り返し解くのに夢中で、そういえば先生が絶対出るって言ってたプリントやってなかった…などということがないように、
「直前の日曜日にプリントをやる」など、見通しを持って計画表に書き込んでおきましょう。
③当日のテストの問題数が多く、難しい問題も出る
小学校のテスト(特にカラーテスト)に出る問題は基本中の基本がほとんど。しかし、中学校の定期テストでは、出題数も多く、知識を活用するような問題も出されることが多いです。
計画力+αで解決!
ー目標点に到達するために何をすべきか考え、工夫するー
高得点をねらう場合は「ただ問題を解き終わればいい」ではなく、時間配分を考えたり、ミスを減らすためにどうするか…
などを考えて取り組み方を工夫する必要があります。

いかがでしたか。
ノートスでは、テスト終了ごとにテスト勉強の振り返りを行います。
5教科まんべんなく点数が高い生徒は、勉強計画の精度もとても高いです。
逆に
特定の教科だけ点数が高い・低い
テストの度に点数の上下が激しい
…などアンバランスが目立つ場合には、いきあたりばったり勉強になっていたり、計画自体にムラがあることが多いです。
目標達成に不可欠な「計画力」は、勉強だけでなく、部活動や習い事の練習やトレーニングにも活用できます。
そして、「自分で計画して行動する」という経験が、大人になってからの「自己管理力」の土台となる大切な経験になります。
この夏から、ノートスで一緒に「計画力」を磨きませんか?
お問合せはHP資料請求ページまたはお電話で☏
◆資料請求ページ↓↓↓
https://notes-35e72.web.app/request/document
◆お近くの校舎の電話番号↓↓↓
https://www.notes-japan.com/school
◆お得なキャンペーン情報↓↓↓
https://www.notes-japan.com/campaign/16186















